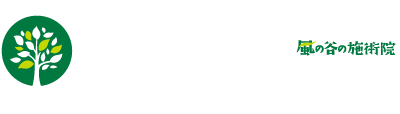私の母が亡くなりました。
H30年9月、77歳の誕生日を迎えたすぐのことでした。
癌が発覚してから、たった1年の出来事でした。
母の人生は私たち子供3人を必死に育て上げるためにだけ生きてきたような人生でした。
普段化粧はなく、着ている服も子供達のお下がりの服をよく着ていました。
寝る前におちょこに一杯のお酒と、図書館で借りてきた本を読むことを人生の唯一の楽しみにしていた方でした。
私が大学を一浪して入社した会社を1年そこらで辞めたときも、何年かフリーターをやっていた頃も、世界中を放浪の旅していたときも、私を否定をせず、唯一応援しつづけてくれたのが母でした。
母が亡くなるまでのしばらくの間、母の世話をさせて頂く上で、私が母の死から学ばせて頂いたことが1つあります。
それは介護の現場を支えている医療介護サービスの尊さです。
私の仕事は、介護サービスを受けているお宅にお宅に毎日伺い、マッサージやリハビリを提供するお仕事です。
日常、介護の現場はいつも当たり前ように目にしています。
ときどきケアマネージャーの方から相談を受けたり、担当者会議にも参加することもあります。
当然のように介護については理解しているつもりでした。
しかし「知っている」と「実際それをやる」とでは大きく異なりなした。
どうしてもこのことを、私が心から尊敬する医療と介護の現場で働く方々にお伝えしたくてこの文章を書きました。
母の死の3ヶ月前くらいでしょうか?
やせ細り、歩行もだんだん難しくなる中、介護保険を本格的に利用するようになりました。
ケアマネジャーの方が自宅に来られるようになり、訪問ドクターの薦めのもと、訪問看護師の方やヘルパーさんが定期的に来て頂けるようになりました。
何とか家の中は歩けていた母も、やがてベッドで寝たきりになりましました。
ほんの半年前までは元気だった母のオムツをまさか私が交換することが訪れるとはまったく想像したこともありませんでした。
母が亡くなる1ヶ月前はとりわけ多忙でした。
在宅酸素が入り、医師、看護師、ヘルパーさんが毎日のように訪れるようになりました。
「自宅で死にたい…」というのが、たった1つの母の希望でした。
普段から「あれがしたい」とか「これが欲しい」など一切の要求を家族に求めたことがなかった母が私たちにもらしたささやかな希望でした。
これだけは何としても母の思う通りにしてけげたい…と考えていた我々家族は、団結して母の介護にあたりました。
亡くなる2週間前には、母の身体が一層痩せて、骨と皮のような状態になっていく一方で、腹水はどんどん溜まっていきました。
痩せてくのにむしろ体重は重くなり、それが骨に当たるため痛さを訴えるようになりました。
自分自身で身体を動かすことも出来なくなり、常に体位変換を求めるようになりました。
母の頭はハッキリしていても言葉を発すること自体も難しくなり、聞き取りが難しい中、必死の訴えを拾い、あれこれと世話にあたりました。
亡くなる1週間にもなれば、その体位変換は昼夜問わず5分置きに訪れました。
私は自宅のある神奈川から仕事を終えると実家のある大阪まで週3~4回、夜行バスと新幹線で行き来して介護にあたりました。
夜は、主に介護していた兄と2人で母の病床の両脇に布団を引いて、交代で介護にたりました。
母の介護の中で一番辛かったことは「寝れないこと」でした。
人は寝れないと、まず失われるのが「判断力」です。
「母を自宅で逝がせてあげたい」
と心では思っていても、身体を睡眠を強烈に求めています。
寝ようとウトウトする中、5分置きに起こされるようになると、母を想っていた気持ちが苛立ちや怒りに変化していきます。
どんなに母のことを想っていても、この感情は訪れるのです。
自分自身の生命が犯されそうにになった時、自分を守るための防衛本能なのだと思いました。
健康な大人が二人掛かりで昼夜交代で介護にあたり、加えて父や長男の兄を介護にあたりましたが、介護の現場はわたしが思い描いた以上に、肉体的、精神的に過酷でした。
たった1人の人間の介護をすることの難しさ知りました。
そのような過酷な環境な中で、母の死が近づくにつれて、訪問医の先生は毎日のように声をかえに様子をみに来てくれました。
訪問看護師の方、ヘルパーの方もオムツの交換から、便の搔き出し、ベッド上の髪の洗浄など事細かところまで我々を助けてもらいました。
そして死に逝く母を介護する私たちへ、死を迎える介護者の心構えや、死を迎えた時の対処方法を教えてくださりました。
1人の人生のエンディングを出来る限り円滑に迎えるサポートをして頂きました。
これも訪問看護も方のお仕事だったのですね。
訪問看護のお仕事は尊い仕事だと思いました。
普段、訪問看護の方ともお仕事でご一緒させていだたくことがありますが、このような現場であることは一切知りませんでした。
母の死を最初に確認したのは、母のベッドの両脇に添い寝して、一緒に介護にしていた兄でした。
早朝6時、母の身体を触ってその冷たさに異変を感じ、私を起こしました。
日曜日の早朝にもかかわらず、看護師、医師が1時間後には訪問ドクターの先生が駆けつけました。
母の着替えと化粧もお世話になった看護師の方にやっていただけました。
彼ら自身、家族との大切な時間を過ごすため、または日常の仕事の身体を休めるための休日です。
仕事とはいえ唯一の休みにもかかわらず、いやな態度を一切見せず、母の亡骸にてを合わせてに訪れて頂いたことに、母の死の悲しさを忘れて、深い感動を感じたことは今でもよく記憶しています。
訪問医療、そして訪問看護の凄さを感じました。
私たち家族が掲げた「母を自宅で逝かせてあげる」というささやかな目標も、この介護サービスそして医師の先生の支えなくしては、決して達成できませんでした。
母の最期を、最後まで見届けて頂いた医師、松宮先生、それから母のすべてを世話してくださった訪問の看護師の方々、ヘルパーの方々、そしてそれを支援して頂いたケアマネジャーの方、私たちを助けて頂き本当にありがとうございました。
それから今もどこかの医療と介護の現場で、人生の最も尊い瞬間を迎える方々のために働いてくださる医師、看護師、ヘルパー、ケアマネジャーの方々、本当にありがとうございます。
佐々木 謙